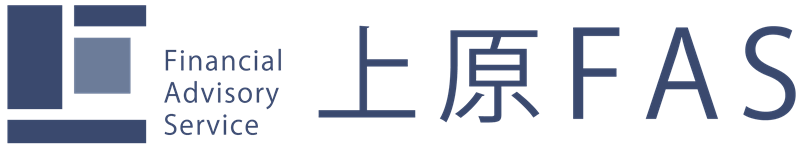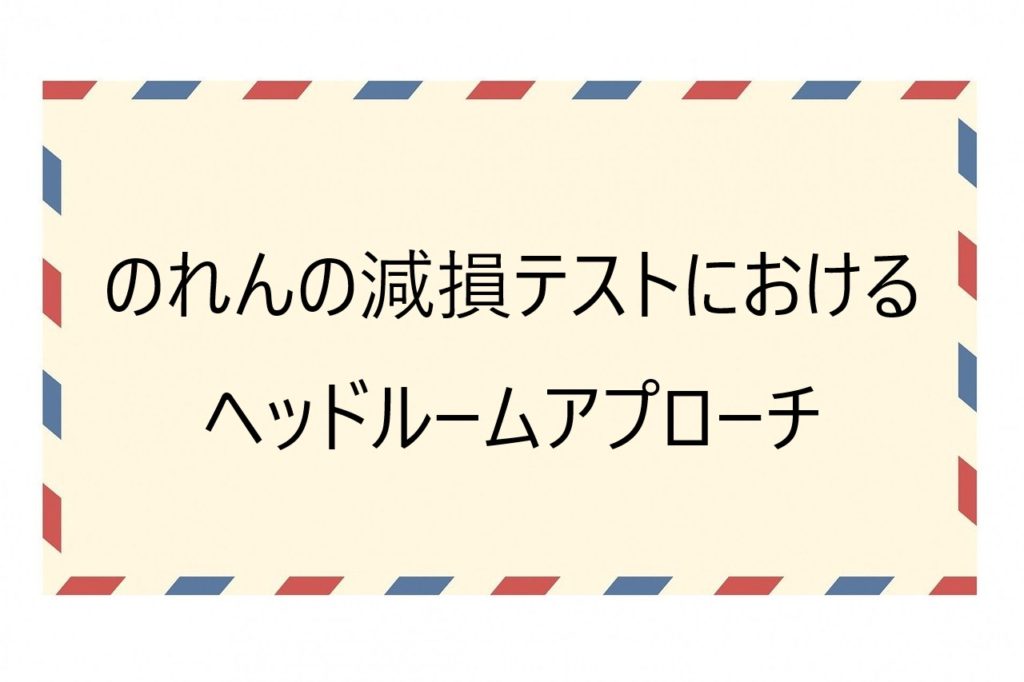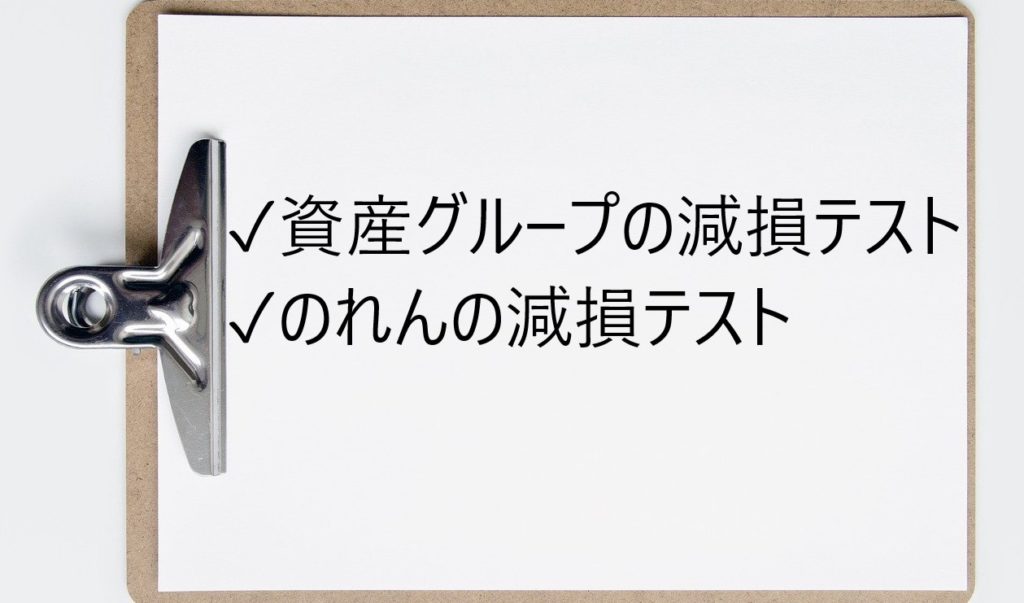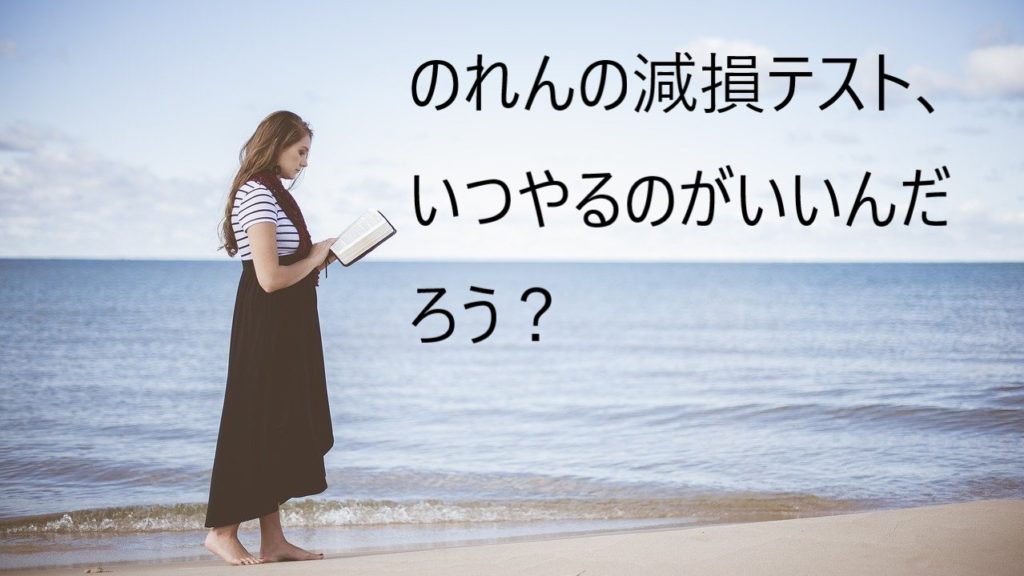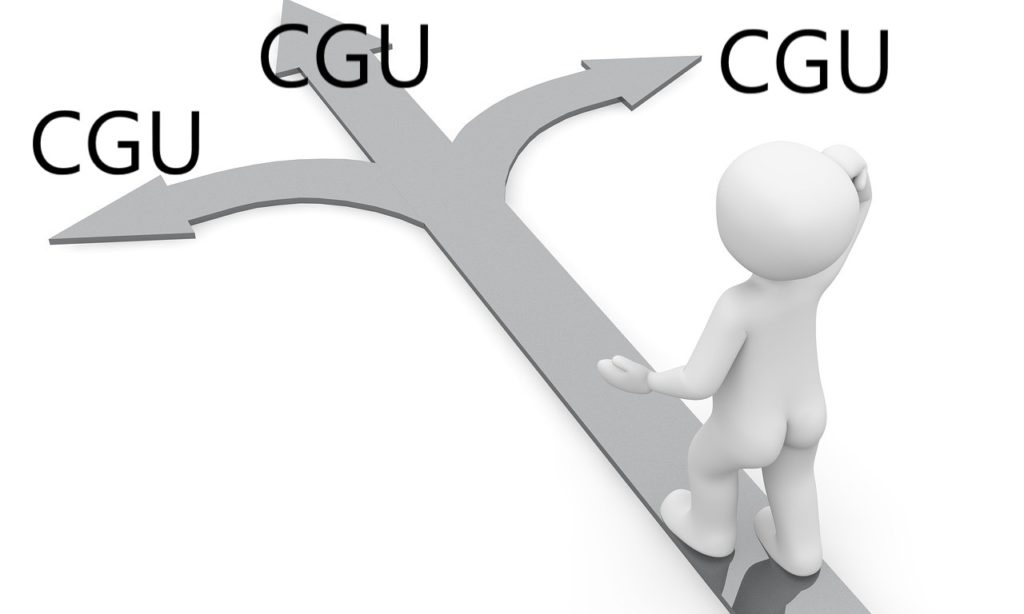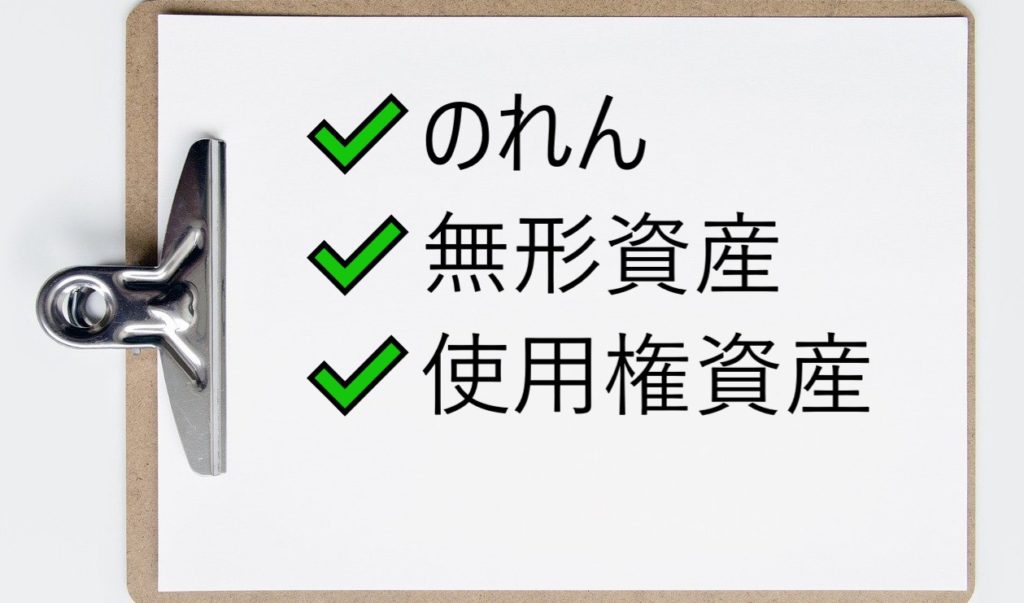減損テスト– category –
-

ヘッドルームアプローチとIFRSののれんの減損テストの目的
2020年3月にIFRS Foundationより公表された「企業結合ー開示、のれん及び減損」(以下ディスカッションペーパーと呼びます)において検討されたのれんの減損テストの手... -

IFRSにおける減損損失の戻し入れ
IAS36号ではのれん以外の減損損失については戻し入れを認めています。あまり実務上見かけることは少ないですが整理してみました。 減損戻し入れは、減損損失の計上と基... -

のれんと資産グループの減損テストの関係(日本基準)
今回のブログでは日本基準におけるのれんと資産グループの減損テストの関係について取り上げます。 減損テストは、簿価と回収可能価額を比較する手続きですが、のれんの... -

IFRSののれんの減損テストの実施時期と減損の兆候
今回のブログではIFRSを前提にのれんを含めた各資産(or資金生成単位)の減損テストをいつ、どのような状況になった時に実施すればよいのかを解説します。 ご存知の方も... -

IFRSにおける持分法の減損テストの実務
持分法投資の減損テストは、投資者から見ると、関連会社株式という金融商品に対する減損テストになります。持分法投資は金融商品という側面を持ちつつも、通常は事業か... -

IFRSののれんの償却等に関するディスカッションペーパー
IASBは、のれんの償却などのディスカッションペーパーを公表しました。のれんの償却については、ボードメンバーの14人中8人が現行の減損のみモデルに賛成したとのことで... -

コロナ禍における減損会計
※コロナの影響を踏まえた会計上の取り扱いは、不定期に新着情報がある状況ですので、新たな情報が開示される都度、ブログを更新していきます。 当ブログは2020年3月13日... -

IFRSの減損テストにおける税前割引率の計算の実務
IFRSにおける減損テストにおいて、回収可能価額を使用価値で計算した場合には、税引前の割引率を開示する必要があります。しかし、一般的に企業価値評価で割引率として... -

IFRSの減損テストにおける資産のグルーピング
グルーピングとは、減損テストを行う単位を決定することです。減損テストは、帳簿価額と回収可能価額を比較して、帳簿価額>回収可能価額となった場合に減損損失を行い... -

減損テストにおける将来キャッシュ・フローの推定(IFRS)
減損テストでは、使用価値や売却費用控除後公正価値を将来キャッシュフロー(以下、CFと略します)の割引現在価値で計算することが多いため、将来CFをどのように見積もる... -

IFRSの減損テストで集計する簿価
のれんの減損テストなど、資金生成単位や資金生成単位グループでの減損テストの場合、資金生成単位等に関連する資産、負債のうちどの勘定科目までを集計すればよいか、... -

日本基準の減損テストで使用する割引率
日本基準に基づく減損テストで採用する割引率は税引前の割引率であるなど、通常の企業価値評価の実務では採用しないような考え方に基づく割引率を計算する必要がありま...
12