企業価値評価の中でメインとなる論点は、事業価値、つまりは評価対象企業の本業から生み出される価値がいくらかです。
ただ、本業とは別に評価対象企業が保有している非事業用の資産も評価対象企業が保有している資産であるため、無視することはできません。
非事業用資産は事業価値ほど論点があるわけではないですが、①時価評価を行うこと②事業価値と重複しないことの2点を留意する必要があります。
今回は、非事業用資産の取り扱いにおいて論点となりそうな項目を勘定科目別に見ていきたいと思います。
価値の概念のおさらい
簡単に企業価値評価の考え方、用語について確認しておきましょう。
- 事業価値:本業の事業の価値です。DCF法では、フリーキャッシュフローを割引計算することで計算します。類似企業比較法では、EBITDAxEBITDA倍率やEBITxEBIT倍率で計算します。
- 企業価値:事業価値に非事業用資産を加算して計算します。企業価値は債権者と株主に帰属する価値となります。
- 株式価値:企業価値から、債権者に帰属する有利子負債の価値を控除して計算します。株式価値は株主に帰属する価値となります。
なお、用語は書籍やファームによって異なりますので、絶対的なものではなく、あくまで本ブログの用語とご理解ください。
本ブログのテーマは非事業用資産の考え方ですので、企業価値を計算する際に出てくるものです。
事業価値、企業価値、株式価値という価値の概念について、より詳細な解説を別ブログにアップしていますので、ご確認ください。

非事業用資産とは
非事業用資産の定義に明確なものはないですが、その名の通り、本業とは直接関係ない資産言い換えると、売却しても本業に影響がない資産といえます。
価値評価の観点から言うと、①事業価値の計算には含まれないものの、②企業にとって価値があるものということができます。
事業価値の計算に含まれない
例えば、同じ土地であっても、どのように価値を計算するかは以下のように3つの方法が考えられ、非事業用資産に含めるか否かはどのように土地の価値をとらえるかによります。
- 事業用の土地:価値はフリーキャッシュフローの中に含まれているため、非事業用資産には含めない。
- 非事業用(例えば投資用)の土地
- フリーキャッシュフローに受取賃料を含めている場合:土地の価値は事業価値に入っているため、非事業用資産とはしない。
- フリーキャッシュフローに受取賃料を含めない場合:非事業用資産として、土地の時価を採用
※DCF法を前提にしています
②-❶のように、非事業用資産であっても、フリーキャッシュフロー計算に含めているのであれば、非事業用資産とはしません(この場合、土地から生み出されるキャッシュフローを事業リスクを考慮したWACCで割り引くことの妥当性の検証が必要になります)。
したがって、事業に供していない土地という情報だけでは、それを価値評価上非事業用資産とするか否かを決定することはできず、事業用資産とするのか非事業用資産とするかはDCF法のフリーキャッシュフローの内容に応じて判断していくことになります。
企業にとって価値がある
当たり前ですが、事業価値の計算に含まれていなくも、企業にとって価値がないのであれば、非事業用資産とはしません。
例えば、全く買い手がいないような遊休の土地などは企業にとって価値があるとは言えません。
また、企業にとっての価値は時価ですので、非事業用資産とする場合はその時価を測定する必要があります。
非事業用資産の勘定科目別の分析
単純に勘定科目だけでは、事業用資産とするか、非事業用資産とするかを判断できないケースも多いため、必要に応じて前提条件を付しつつ解説します。
現預金
現預金は事業用必要な部分(必要現預金)と事業上保有していることが必須ではない部分(余剰現預金)に分類し、余剰現預金は非事業用資産とすることが一般的です。
難しいのは、どのように必要現預金の水準を決定するかです。
決め方にルールはありませんが、M&Aの局面であれば、財務DDレポートの調査結果を参照したり、経営者の方にインタビューを行って確認することが一般的です。
現預金のうち、例えば定期預金はその性質からいって余剰現預金に分類できると考えられます。
有価証券、投資有価証券、出資金など
非事業用資産として、その時価を非事業用資産とすることが一般的だと思います。
例えば持ち合い株式等で売却が困難な有価証券もあるとは思いますが、本当に資金繰りに困った時にまで売却できないということはまれだと思いますので、保有している有価証券の価値はいくらか?という観点からは、非事業用資産とすることが望ましいと思います。
時価がない株式等については、純資産x持分比率等で代替することも多いと思います。
また、売却した場合には税効果が発生しますので、時価と簿価の差額について、税効果を加味することも多いと思います。
とはいえ、同業者団体の加盟金のような、事業を継続する限り払い戻しを受けれないようなものや、どうしても売却できない持ち合い株式は、受取配当金をフリーキャッシュフロー計算に織り込み、非事業用資産とはしないことも有りうると思います。
預け金
性質次第ですが、グループ会社間のファイナンス目的のための預け金であれば、非事業用資産とすることが多いと考えられます。ただし、必要な資金まで預け金にしている場合は一定程度は非事業用資産とはしないケースもあると思います。
売掛金、棚卸資産
売掛金、棚卸資産は事業用資産の最たるものですので、非事業用資産とすることはないと思います。
貸付金
非連結子会社に対する貸付金や、役員、従業員に対する貸付金の場合、回収可能性があるのであれば、非事業用資産とすることが一般的ですが、回収可能性が怪しい場合は慎重に検討する必要があると思います。
有形固定資産・無形固定資産
有形、無形固定資産も事業用資産の最たるものものですので、非事業用資産とすることは基本的にはありません。
ただし、賃貸しているもの、遊休資産となっているものについては、フリーキャッシュフロー計算に含めないのであれば、その時価を企業価値の加算項目とします。
賃貸収入をフリーキャッシュフロー計算に含めるのか、時価をもって非事業用資産とするかはケースバイケースです。
評価対象会社がなぜその資産を売却せずに賃貸にしているのかや、今後の売却可能性等を勘案して、どちらで測定することがより実態に合っているのかを分析して判断することになります。
例えば工場と隣接していて売却できない場合などの状況では、売却を前提とした時価で非事業用資産とすることは実態に合わないと思います。
関連会社株式
持分比率を考慮した持分法適用会社のフリーキャッシュフロー(or持分法投資損益)をフリーキャッシュフロー計算に含める方法と、持分法投資の時価(or純資産x持分比率など)を非事業用資産とする方法の2つがあります。
これもどちらが正解という話ではなく、今後の方針や、どちらで測定することがより実態に合っているのかを分析して判断することになります。
保険積立金
通常は、解約返戻金の金額を時価とみなして非事業用資産とすることが多いと思います。
敷金
将来的に賃貸借契約を解除して払い戻しを受けることが見込まれる部分は、フリーキャッシュフロー計算に織り込むことが一般的です。
他方で、事業計画期間ないし、継続期間において払い戻しを受けることが見込まれない部分は、回収可能性がないため、フリーキャッシュフロー計算にも含めず、非事業用資産にも含めないことが一般的だと思いますす。
繰延税金資産
フリーキャッシュフロー計算に織り込むことが一般的ですが、実務上は金額が大きなもののみ考慮し、インパクトが大きくない繰延税金資産(一時差異)は無視することが多いと思います。
繰越欠損金については、次を参照ください。
繰越欠損金
繰越欠損金は将来の節税額をフリーキャッシュフロー計算に織り込むことが一般的です。
なお、会計上の繰延税金資産は、会計上のルールに基づく計算方法であり、企業価値評価においては、会計上のルール(繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針における分類等)は考慮しません。
退職給付にかかる資産/前払年金費用
読者の方に質問をいただいた勘定科目です。
非事業用資産として扱う考え方と非事業用資産とはしない考え方の2つがある科目だと思います。
非事業用資産とはしない派の論拠は、退職給付にかかる資産は企業が自由に処分できる資産ではないではないことを論拠としていると考えられますが、さはさりながら退職給付にかかる資産が100のA社と1,000のB社場合、(他の前提条件が同一であれば)当然B社の方が株式価値が高くなると想定されますので、個人的には非事業用資産とする考え方の方が腹落ちします。









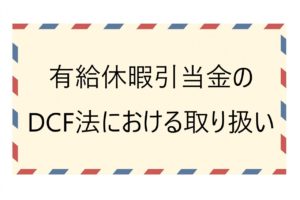



コメント
コメント一覧 (2件)
具体例や計算例と共にわかりやすい説明、ありがとうございます。
質問なのですが、BSの資産側に「退職給付に係る資産」(日本基準かつ単体の場合は「前払年金費用」)がある場合、これは非事業用資産として取り扱うのでしょうか?
ご質問ありがとうございます。
退職給付にかかる資産については、非事業用資産として扱う考え方と非事業用資産とはしない考え方の2つがある箇所かと思われます。
後者は退職給付にかかる資産は企業が自由に処分できる資産ではないではないことを論拠としていると考えられますが、さはさりながら退職給付にかかる資産が100のA社と1,000のB社場合、(他の前提条件が同一であれば)当然B社の方が株式価値が高くなると想定されますので、個人的には前者の考え方の方が腹落ちします。